サントリー美術館で開催されている 「エミール・ガレ 憧憬のパリ」に 行ってきました。

この記事は…
1.エミール・ガレとはどのような人物か
2.心に残った作品3つ紹介
3.終わりに
で構成されています。
ポスターの写真とオレンジ色のデザインに惹かれてサントリー美術館へ。
エミール・ガレについては知識はゼロでしたが、とにかくポスターを見て行きたくなりました。エミール・ガレ(1846~1904)はフランス北東部ロレーヌ地方の古都ナンシーに生まれ、ガラス、陶器、家具において様々な作品を作り出した人物。1904年の58歳のときに白血病によってこの世を去っています。
はたしてエミール・ガレはどのような人物でどのような作品があるのでしょうか。
ガレとはどのような人物か
展示品はガレの初作品から晩年の作品まで時系列順に並んでいます。初めの頃の作品から、既にどれも繊細な絵やガラスに彫られた模様が美しいものばかりでした。
展示室を進んでいくと、ガレは日本芸術、中国「清」のガラス作品、イスラーム芸術といった他国の文化を積極的に取り込んでいく様子が伺えます。さらに植物学、海洋学を修めていたガレはそれらも作品に反映させていきます。
葛飾北斎の鯉が描かれた花器や黒色ガラスを用いた水墨画のような作品もあり、どこか日本を感じる作品も多く親近感を感じられます。
さらにガレは自らガラスの新たな技法を生み出し作品を作っていきます。展示にはガレが使用した技法を紹介する解説もあるのでわかりやすくて良かったと思います。
今回の展示品を見ていく中で私は、ガレという人物は常に探求を続け、自分の作品の可能性を広げていく そのような人物に感じられました。
心に残った作品紹介
今回の展示で心に残った作品を3つ紹介したいと思います。
①花器「蜻蛉」 作者:エミール・ガレ 作成年:1889年 所蔵者:サントリー美術館
蜻蛉=とんぼ

1889年はフランス革命から100年という記念すべきパリ万博の時期になります。
ガレは前回の1878年のパリ万博にも作品を出展し、高い評価を得ていました。それから約10年、ガレはさらに技術を深めていき輝かしい名声を得ていきます。
その中で作成された 花器「蜻蛉」。
黒色ガラスというものが使われている作品で、黒色ガラスには「悲しみ 生と死 闇」といった感覚を思わせるものでそれまであまり使われてこなかったガラスになります。それをガレは積極的に使っています。
花器の鶴首(細長い所)から下に向かって蜻蛉の胴体が伸びていて、花器のふくらんだ所に大きく蜻蛉の姿が描かれています。蜻蛉の翅はとても弱弱しく、1枚の翅はもがれています。 蜻蛉の顔は輪郭が崩れ、生命の終わりを感じます。
写真では分かりづらいですが、花器の底に広がる黒は水面を表していて、そこには水面に力なく浮かぶ蜻蛉がうっすらと描かれています。
私がこの作品から「暗く美しい物語」を感じました。
花器の鶴首からぐねぐねと力無く伸びる胴体を辿っていくと、大きく描かれた蜻蛉が現れます。蜻蛉は力強いタッチでしっかりと描かれていますが、その姿はあまりにも弱弱しいものになっています。先ほどまで生きて飛んでいた蜻蛉の命の糸が切れ、力なく落下していく様子。そして水面に消えるように描かれた蜻蛉の姿。
一つの花器の中に蜻蛉の生と死を描いているこの花器が私の心に残りました。
この花器にガレは「ひとりぼっちのわたし ひとりぼっちでいたい」という刻文を入れています。輝かしい成功をしていたガレが作り出した悲しみの花器、当時のガレの背景が気になります。
②脚付杯「蜻蛉」 製作者:エミール・ガレ 作成年:1903年ー04年 所蔵者:サントリー美術館

蜻蛉はエミール・ガレを象徴するもので彼の生涯の作品の中で度々登場します。ヨーロッパでは蜻蛉は不吉な物、気味の悪い物、忌み嫌われる物として考えられていました。逆に日本では益虫、勝虫として考えられていました。その中で、日本美術にも造詣が深かったガレは蜻蛉に何かを感じたのかもしれません。
脚付杯「蜻蛉」は1903年~1904年はガレの最晩年に作成されました。白血病に冒される中、自分の死期を予感したガレが友人や親戚に贈ったものの一つになります。
白色のガラス杯に描かれた立体的な蜻蛉、その蜻蛉の影が杯の中に描かれています。ガレの培ってきた技法が詰め込まれたこの作品は展示会の最後に飾られています。
この作品の図録の解説には、ガレの象徴する蜻蛉を描くことによってガラスの中に生きたいガレの心情を物語っているのかもしれないとされています。
様々な解釈があると思います。その中で私の感じたものを書こうと思います。
私はこの作品を見た時、希望のようなものを感じました。明日に向かっていくような、死期を悟ったガレがそれでも前に進むために自分の思いを込めた作品に感じました。
①で紹介した黒色ガラスの蜻蛉のように死に向かって落ちていくのではなく、生き生きと水面を自由に飛ぶ蜻蛉に私は生命の輝きを感じられます。杯の足についた白い楕円形のものは蜻蛉の卵のように感じられます。
白血病に冒されながらも、自らの生をまっとうしようとするガレの力強さをこの作品から感じられました。
③ランプ「ひとよ茸」 作成者:エミール・ガレ 作成年:1902年頃 所蔵者:サントリー美術館

今回の展示会のポスターに描かれている作品で、展示会の終盤にオレンジ色に煌々と輝いている作品。
ヒトヨ茸はその名前の通り、一夜で成長し枯れるキノコでガレはその成長過程を3段階に分けて表現しています。
一番手前の成長前の茸は一番明るく輝いていて生命の輝きを感じます。
真ん中の茸は手前と奥の茸と比べて色合いがすこし柔らかで、弱弱しさがあり、成長途中と枯れ途中のどちらの様子も感じられます。
一番奥の成長した茸は深いオレンジ色で大きく傘を開いていて、大人のような落ち着いた風合いがあります。またこの茸の下に1番目と2番目の茸が入り込んでいて、まるで子供を守るような姿にも感じられます。
それぞれの茸の軸の部分にも違いがあり、そこも見どころだと思います。手前の茸の軸は大きく捻じれたような模様、真ん中の茸はまっすぐな模様、奥の茸は緩やかなカーブの模様。それぞれの段階での差異がありじっくり見るのをお勧めします。
以上の3点が私の心に残った作品になります。他にも素敵な作品たくさんあるので皆さんのお気に入りの一つを見つけてみてください。
終わりに
初めてのエミール・ガレ展でしたが、初期の作品から晩年の作品までの時系列がしっかりしているためガレがどのような道を歩んできたのかが分かる展示会でした。
作品の展示の仕方も360度から見れるものが多く、角度によって見え方が異なるためより楽しめました。
また全ての作品撮影が可能なため、気に入った作品を記録に残せるのもよかった点になります。シャッター音が気になるという人はサントリー美術館は静寂鑑賞時間を設けているようなのでその時間帯に行くといいかもしれません。
サントリー美術館には子供向けのワークシートがあります。大人でも十分に楽しめる作りになっているので一人でも、子供と一緒に見て回ってもより深く作品と向き合えて楽しいと思います。
「エミール・ガレ 憧憬のパリ展」は2025年4月13日までなので気になった方は是非行ってみてください。コメント欄に感想等書いていただけたら嬉しいです。

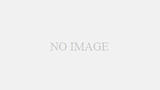
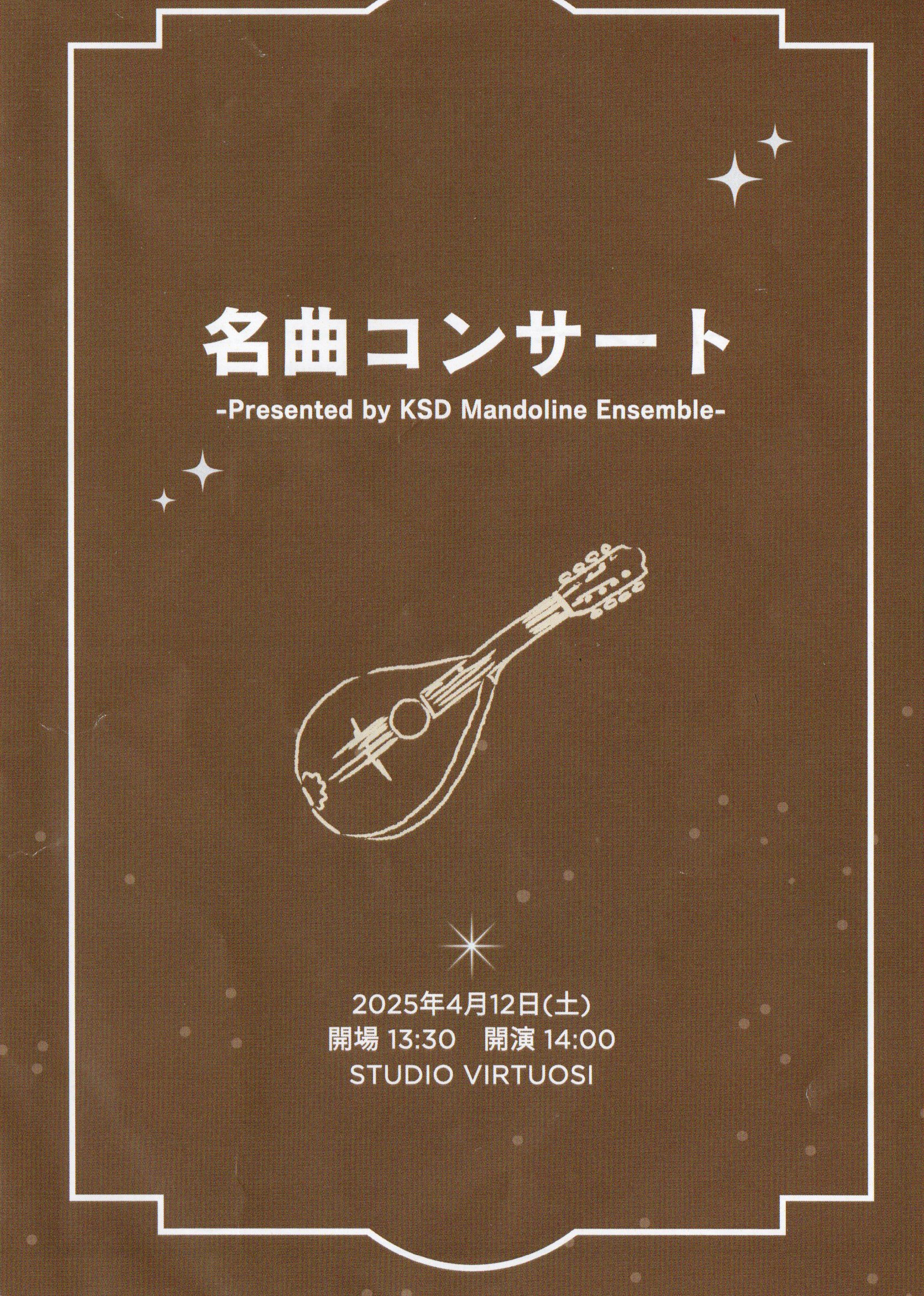
コメント